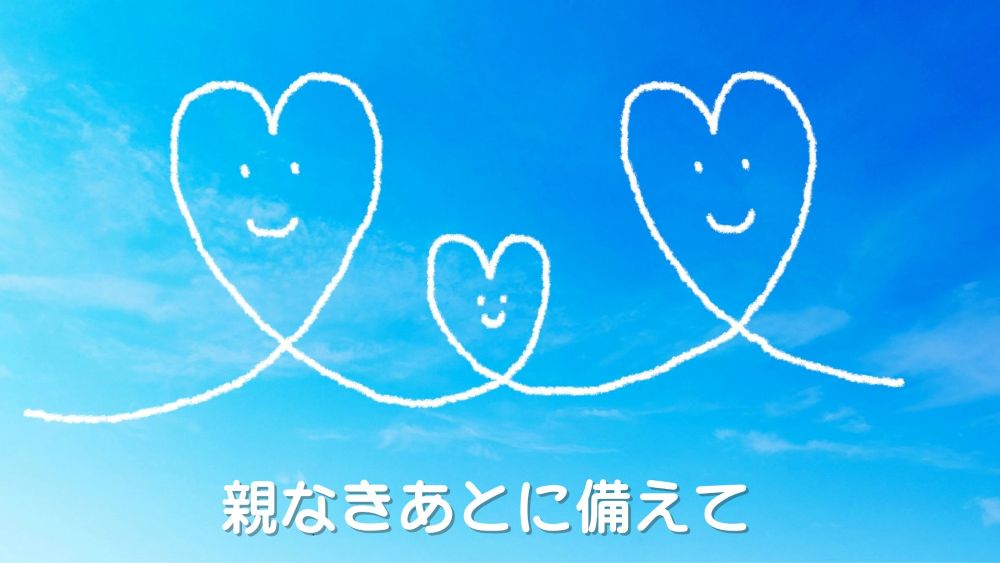
親なきあとに備えて、できることから備えましょう
「親なき後」の暮らしに備えるためには、どうしてもサポートを受ける必要があります。
「親なきあと」のことは、親がいくら頑張っても限界があり、無理です。なぜなら、親がいなくなった後のことですから、したがって、「親なきあと」のことは、親ではなく、各自治体などの各種機関の力をお借りするしかありません。各自治体などの各種機関のサポートを受けずに、子供の将来は想像できません。サポートを受けれることができることは、遠慮なくサポートをお願いしましょう。
しかし、そのサポートを受けるためには、障害者手帳が必要となります。
障害者手帳なしには、サポートを受けることは、難しいです。
障害者手帳を持つことで、さまざまなサービスが受けやすくなり、現在や将来の暮らしの安心、安全にもつながりますので、障がい者手帳を取得しておくことをお勧めします。
手帳は3種類
- 身体障害者手帳
- 養育手帳
- 精神障害保健福祉手帳
「親なき後」に備えるには、相続への備えが重要です。
今すぐできることは、親なきあと、相続で遺産分割協議をしなくて済むように備えることです。
- 親のどちらかでも亡くなると、土地建物の名義変更や銀行口座の解約や名義変更などの、いろいろな相続手続きが、必ず必要になります。
- この相続手続きのため、一般的には相続人全員で、遺産分割を協議し、相続人全員の同意を得て、遺産分割協議書を作成して、この遺産分割協議書で相続手続きを進めて行きます。
- しかし、もし、障害(判断能力が不十分)がある子が相続人の一人になる場合、ここから問題が発生します。
- まず、障害(判断能力が不十分)がある子は、遺産分割協議に参加することができません。理由は、判断能力に問題がある場合、その方の利益が害される恐れがあるからです。
- そこで、遺産分割協議に際し、その方のために、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てをすることになります。
- 成年後見人に対し何も対策していないで申立てした場合、家庭裁判所は通常、家庭の事情を何も知らない、見ず知らずの弁護士や司法書士などの専門職の人を成年後見人に選任します。
- 判断能力が不十分な人に、一度成年後見人が選任されると、以降、取り消すことはできませんし、そこから、その方の判断能力が回復するか、亡くなるまで、一生、成年後見人に対し毎年費用が発生します。
- 成年後見人は、判断能力が不十分な方の利益を最優先に考えますので、遺産分割協議の際に、成年後見人はその方のために、法定相続分の財産分与を請求するでしょう。そして、その方が相続した財産を含むすべての財産はすべて、そこから一生、成年後見人が管理することになります。
- そこで、今からできることは、親に相続が発生した際に、遺産分割協議をせずに、相続手続きができるようにするように備えておくことが重要です。
- 一番簡単で手軽なのが、遺言書を作成して残しておくことです。といっても、遺言書に法的効力を持たせるには、法律にそって遺言書を作成する必要があります。(詳細は別途発信します)
- お父さん、お母さんがご健在でしたら、お父さんは、お母さんにすべての財産を相続させる遺言書を作成し、お母さんは、お父さんにすべての財産を相続させると遺言書を作成する、といった具合に遺言書を作成することで、親の相続が発生した際に、判断能力が不十分な子に成年後見人を選任することを、できる限り先延ばしすることができます。
- 親なき後に備えるのに、障害(判断能力が不十分)がある子に、いずれ成年後見人を選任することは、避けられないと思いますが、成年後見人の選任は慎重に時間をかけて行いましょう、今からできれば信頼できる、ご家庭事情が分かっていて、お子さん障害のことや性格を分かってくれる、専門家を探しておき、いざという時、お子さんの成年後見人の候補者になってもらえるよう依頼しておくとよいです。
初回相談無料 お気軽にお問い合わせください048-738-3557営業時間 9:00-17:00
メールでのお問い合わせ